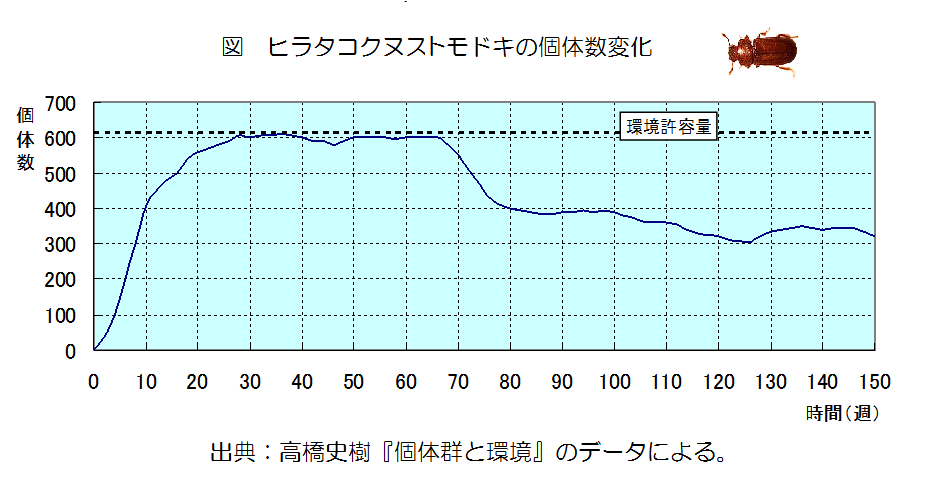動物の場合、これら4つの抑制行動は、いずれも遺伝的に引き継がれている行動要因、つまり本能的、あるいは生得的な装置に従っています。生得的とは遺伝情報がその動物に予め組み込まれているという意味で、逆にいえば動物の意思(それがあるか否か、それ自体が問題ですが)とは、ほとんど無関係に機能しているということです。
ところが、人間の場合は、「本能が欠如した動物」(日高敏隆:1930~2009)とか「本能が壊れた動物」(岸田秀:1933~)といわれているように、本能によって対応する方法を著しく欠いています。文化という能力を持ったがゆえに、本能の働く力が薄れている、といってもいいでしょう。となると、4つの行動はどのように変化しているのでしょうか。
①の生殖・生存力抑制については、人間の場合もほとんど動物と同じです。食糧不足、環境悪化、高ストレスに晒されていると、精神的・肉体的に体力が低下し、一方では精子減少、排卵減少、性交不能、不妊症、生理不順、流産・死産の増加といった生殖能力の低下が顕著になり、他方では病気の増加、寿命の低下、胎児・乳幼児の死亡率増加といった生存能力の低下現象が発生してきます。
これらはいずれも、人間という〈種〉に備わった生殖・生存力の抑制行動であり、その意味では他の動物と共通する遺伝的、生得的な抑制装置といえるでしょう
しかし、②生殖・生存介入、③生殖・生存格差化、④集団離脱については、人類の歴史を振り返ると、民族や時代によって極めて多種多様な方法がとられており、必ずしも遺伝的、生得的とはいえないようです。

例えば、堕胎(妊娠中絶)、間引き(嬰児殺し)、避妊、あるいは棄民や姥捨て(老人遺棄)といった直接的な次元はもとより、性交禁止や結婚禁止などのタブーや慣習といった間接的な次元、あるいは集団逃亡、強制移民といった離脱的な次元まで、人間はさまざまな方法で対処していますが、そこには民族や時代の世界観が色濃く反映されています。

その意味で、これらの行動は人間に特有な言語的、象徴的能力、つまり広義の「文化」に基づいているというべきでしょう。
とすれば、人間にとって、②~④は遺伝的、生得的な行動ではなく、後天的、人為的な行動ということなります。他のさまざまな行動と同様に、人口抑制についても、人間は「文化」という独自の方法を援用しているのです。
このように考えると、人間の人口抑制装置は、生物的(=生理的)次元と人為的(=文化的)次元の二重構造になっている、といえるでしょう。
注:二重構造については、BLG生活学マーケティングを参照のこと。
(詳しくは古田隆彦『日本人はどこまで減るか』)